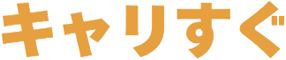不動産鑑定士の仕事内容は評価や調査!やめとけといわれる3つの理由も解説
2025/05/06
投稿者:武藤翼

「不動産鑑定士ってどのような仕事をしているの?」と疑問に思ったことはありませんか?
不動産鑑定士は、土地や建物などの不動産の経済的価値を判定・評価する専門家です。
本記事では、不動産鑑定士の具体的な仕事内容から年収、資格取得の難しさまで詳しく解説します。
不動産鑑定士は、単に不動産の価格を決めるだけでなく、コンサルティングや調査・分析など多岐にわたる業務を担当しています。
全国でわずか8,000人ほどしかいない希少価値の高い資格であり、平均年収は約750万円と高水準です。
一方で、最終合格率が5%と低く、試験に合格後も実務修習が必要など、資格取得までの道のりは決して平坦ではありません。
この記事を読めば、不動産鑑定士という職業の全体像が把握でき、自分に合った職業か判断する材料になるでしょう。
不動産鑑定士の仕事内容4つ
不動産鑑定士の主な仕事内容は以下の4つです。
- 不動産の鑑定評価
- コンサルティング
- 調査・分析
- 国際評価(海外物件の評価)
順番に解説します。
不動産の価値を決める鑑定評価
不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士の中心的な業務であり、独占業務として法律で定められています。
土地や建物の経済価値について、周囲の地理的状況や法規制、市場経済における価値などさまざまな要素を考慮して鑑定評価を行い、「不動産鑑定評価書」というレポートにまとめます。
具体的な業務内容は、以下のとおりです。
- 公的評価(地価公示、都道府県地価調査、相続税標準地・固定資産税標準宅地の評価など)
- 民間評価(不動産取引における鑑定評価、担保評価、証券化に関する評価など)
- 裁判所の競売に関わる評価
- 公共用地取得に関する評価
鑑定評価を行うためには、不動産に関する法律の知識はもちろん、経済学や会計学の知識も必要です。
現地調査や過去の取引事例の分析など、実務的なスキルも求められます。
不動産業界での実務経験がある方は、この分野での活躍が期待できるでしょう。
コンサルティング
不動産鑑定士は、鑑定評価で培った専門知識を活かして、不動産に関するコンサルティング業務も行います。
個人や企業を対象に、不動産の有効活用や開発計画に関する相談に応じ、総合的なアドバイスを提供します。
コンサルティング業務の具体例は、以下のとおりです。
- 土地の最適な利用方法の提案
- マンション建替えに関するアドバイス
- 市街地再開発事業における権利調整
- 不動産投資に関する相談
- 企業のCRE(企業不動産)戦略の立案支援
業務においては、不動産の専門知識だけでなく、コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力も重要です。
クライアントのニーズを正確に把握し、最適な解決策を提案できる能力が求められます。
創造的な思考力を持ち、新しいビジネスモデルを構築できる人材が活躍できる分野でもあります。
調査・分析
不動産鑑定士は、不動産に関するさまざまな調査・分析業務も担当します。この業務は鑑定評価やコンサルティングの基礎となる重要な仕事です。
主な調査・分析業務としては、以下が挙げられます。
- 不動産の取引価格水準の把握
- 地代・家賃などの水準調査
- 不動産売買や担保価値把握のための調査・分析
- 不動産投資や処分に関連する調査・分析
- 判断資料としてのレポート作成
主に、データ収集能力や分析力が求められます。市場動向を的確に把握するための洞察力も必要です。
統計学の知識や、データ分析ツールの使用スキルがあると有利でしょう。不動産市場の動向に敏感で、数字を扱うことが得意な人に向いている仕事です。
国際評価(海外物件の評価)
グローバル化が進む中、海外不動産の評価需要も増加しています。
不動産鑑定士は国際評価の分野でも活躍しています。国際評価の主な業務は、以下のとおりです。
- 海外に存在する不動産物件の調査・評価
- 国内投資家の海外不動産投資支援
- 海外投資家の国内不動産投資支援
- クロスボーダー取引における価値評価
- 国際基準に基づく不動産評価
業務では、語学力(英語)や国際的な不動産市場の知識が必要です。各国の法制度や商習慣の違いを理解することも重要です。
グローバルな視点を持ち、異文化コミュニケーション能力がある人に適しています。海外での勤務経験や留学経験がある方は、この分野での活躍が期待できるでしょう。
不動産鑑定士の平均年収は750万円
不動産鑑定士の平均年収は約754万円と、一般的な給与所得者の平均年収443万円と比較して高水準です。
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、不動産鑑定士の平均月収は約49万円、年間賞与は約166万円となっています。
年齢別の年収を見ると、キャリアを積むにつれて収入が上昇する傾向があります。
| 年齢区分 | 金額(万円) |
|---|---|
| 〜19歳 | 267万円 |
| 20〜24歳 | 324万円 |
| 25〜29歳 | 435万円 |
| 30〜34歳 | 497万円 |
| 35〜39歳 | 595万円 |
| 40〜44歳 | 602万円 |
| 45〜49歳 | 698万円 |
| 50〜54歳 | 658万円 |
| 55〜59歳 | 673万円 |
| 60〜64歳 | 525万円 |
| 65〜69歳 | 433万円 |
| 70歳〜 | 328万円 |
出典:不動産鑑定士 - 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))
不動産鑑定士の収入は勤務形態によっても大きく異なります。
勤務鑑定士として会社に所属する場合、初年度の年収は600万円から800万円程度ですが、経験を積むと1,000万円を超えることも珍しくありません。
一方、独立開業した場合は、個人の営業力や顧客との関係によって収入に大きな差が出ます。成功すれば年間数千万円の売上を達成することも可能です。
勤務地域によっても収入に差があり、東京や大阪などの大都市圏では需要が高く高収入が期待できる一方、地方では相対的に収入が低くなる傾向があります。
不動産鑑定士は希少価値の高い資格であるため、専門性を活かした安定した収入を得られる職業といえるでしょう。
不動産鑑定士をやめとけといわれる3つの理由
不動産鑑定士は高収入で社会的信頼も厚い職業ですが、「やめとけ」と言われることもあります。その主な理由は、以下の3つです。
- 最終合格率が5%と低い
- 試験に合格しても免許取得までに最短で1年かかる
- 新規参入の障壁が高い
順番に解説します。
最終合格率が5%と低い
不動産鑑定士試験の最終合格率は約5%と低く、「やめとけ」と言われる大きな理由の1つです。
この試験は短答式試験と論文式試験の二段階で構成されており、短答式試験の合格率は約32%、論文式試験の合格率は約14%です。
両方に合格するため、最終的な合格率は極めて低くなります。
試験の難しさは主に以下の点にあります。
- 出題範囲が広い(不動産関連法規、民法、経済学、会計学など)
- 各科目に「足切り」があり、1つでも基準点に達しないと不合格
- 論文式試験では高度な専門知識と論理的思考力が求められる
- 合格に必要な勉強時間は2,000〜4,000時間と言われている
不動産業従事者でも経営者以外はあまり馴染みのない経済学や会計学を学ぶ必要があるため、幅広い知識の習得が求められます。
このような高い難易度のため、多くの受験者が何年も挑戦を続けることになり、精神的・時間的な負担が大きいのです。
試験に合格しても免許取得までに最短で1年かかる
不動産鑑定士試験に合格しても、すぐに不動産鑑定士として活動できるわけではありません。
合格後には「実務修習」と呼ばれる研修期間が必要で、これには最短でも1年、場合によっては2年かかります。
この点も「やめとけ」と言われる理由の1つです。
実務修習の内容は、以下のとおりです。
| 講義 | 内容 |
|---|---|
| 不動産の鑑定評価に関する実務知識の習得 | |
| 基本演習 | 鑑定評価報告書の作成手順の習得 |
| 実地演習 | 実際の鑑定評価報告書作成を通じた評価方法の習得 |
| 修了考査 | 口頭試問および小論文による試験 |
この期間中は研修生として不動産鑑定事務所などに所属し、指導鑑定士の下で実務を学びます。
しかし、この間の収入は一般的に低く、経済的な負担が大きいことが課題です。
実務修習先を自分で見つける必要があり、地方では修習先が限られているため、転居を余儀なくされるケースもあります。
このように、試験合格後も長期間の研修と経済的負担が続くため、資格取得までの道のりは長く険しいものとなります。
新規参入の障壁が高い
不動産鑑定士として独立開業を目指す場合、新規参入の障壁が高いことも「やめとけ」と言われる理由の1つです。以下のような障壁があります。
- 初期費用が高額(事務所開設に500万円以上必要)
- 顧客獲得の難しさ(大手不動産会社や金融機関との取引には実績が必要)
- 報酬単価の下落傾向(価格競争の激化により採算が厳しい)
- 地方では求人自体が極めて少ない
独立開業の場合、安定した収入を得るまでには相当の時間がかかります。
取引先の開拓や信頼関係の構築には最低でも2〜3年を要し、その間の運転資金も確保しなければなりません。
大手不動産鑑定事務所では新規採用を極めて抑制的に行っており、年間1〜2名程度の採用に留まることが多いです。
さらに、地方都市を中心とした地価の下落傾向により、不動産取引や担保評価の需要が減少しています。
地方の鑑定士は深刻な業務量の減少に直面しており、収入の確保に苦慮しているケースが増えています。
このような状況から、新規参入者が安定した収入を得ることは年々困難になっており、長期的な視点での計画が必要です。
不動産鑑定士になる方法
推奨勉強時間は以下のとおりです。
| 試験区分 | 期間 | 1日あたりの勉強時間 | 総勉強時間目安 | 初学者/経験者の違い |
|---|---|---|---|---|
| 短答式試験(初学者) | 10~12ヶ月 | 平日:2~3時間 休日:5~6時間 |
800~1,000時間 | 基礎から体系的に学習が必要 |
| 短答式試験(経験者※) | 6ヶ月 | 平日:2時間 休日:4時間 |
500~700時間 | 関連知識があり効率的に学習可能 |
| 論文式試験 | 6~8ヶ月 | 平日:3時間 休日:6~8時間 |
1,000~1,200時間 | 記述力・論述力の強化が必要 |
※経験者:宅建士資格保有者、不動産業界経験者、金融機関勤務者など
また、学習に向けた参考書やサポートツールなどは以下のとおりです。
| リソース種類 | おすすめポイント |
|---|---|
| 基本テキスト | ・体系的に学べる市販の専門書 ・不動産鑑定評価基準解説書 ・各科目の入門〜中級レベルの教材 |
| 問題集 | ・過去問題集(5年分以上) ・予備校の模擬問題集 ・演習問題集 ・計算問題特化型問題集 |
| 学習サポート | ・予備校の講座(対面/通信) ・添削指導サービス ・スタディグループの活用 ・オンライン学習コミュニティ |
| 学習ツール | ・国土交通省のサイト(過去問公開) ・不動産鑑定士協会の情報 ・受験者向け情報サイト ・スタディサプリなどの学習アプリ |
| その他ツール | ・学習管理アプリ ・デジタル暗記カード ・条文検索ツール ・スケジュール管理ツール |
合格するために継続的な学習や、計画を立てましょう。
不動産鑑定士に関するよくある質問
不動産鑑定士を目指す方や興味を持つ方から、よく寄せられる以下の質問へ回答します。
- 就職先はどのような企業がありますか
- 不動産鑑定士に向いている人の特徴は何ですか
- 不動産鑑定士はきついですか
順番に回答します。
就職先はどのような企業がありますか
不動産鑑定士の主な就職先は多岐にわたります。
主要な就職先としては以下のような選択肢があります。
| 業種 | 例 |
|---|---|
| 不動産鑑定事務所 | 大手鑑定事務所(日本不動産研究所など) ・ 中小規模の鑑定事務所 ・ 個人事務所 |
| 不動産関連企業 | デベロッパー(三井不動産、三菱地所など) ・ 不動産仲介会社 ・ 不動産管理会社 |
| 金融機関 | 銀行(不動産融資部門) ・ 信託銀行 ・ 不動産投資顧問会社 |
| コンサルティング会社 | 不動産コンサルティング会社 ・ 総合コンサルティングファーム |
| 公的機関 | 国土交通省 ・ 地方自治体 ・ 公的不動産評価機関 |
| その他 | 鉄道会社(駅前開発部門) ・ 商社(不動産部門) ・ 一般企業のCRE(企業不動産)部門 |
不動産鑑定士は独立開業も可能で、経験を積んだ後に自らの事務所を設立するケースも多くあります。
独立後は公的評価(地価公示など)の仕事を安定的に受注しながら、民間からの依頼も受けるというスタイルが一般的です。
就職市場では、不動産鑑定士の資格は高く評価されており、大都市圏では需要が高い傾向にあります。
ただし、地方では求人が限られる場合もあるため、地域による差があることを念頭に置く必要があります。
不動産鑑定士に向いている人の特徴は何ですか
不動産鑑定士に向いている人には、以下のような特徴があります。
- 論理的思考力がある
- 責任感が強い
- 継続的に学ぶ姿勢がある
- 細部に注意を払える
- コミュニケーション能力が高い
この特徴を持ち合わせている方は、不動産鑑定士として活躍できることが多いでしょう。
不動産や建築、法律、経済などの分野に興味がある方も、この職業に向いていると言えます。
不動産鑑定士はきついですか
不動産鑑定士の仕事には、きつい面と充実感を得られる面の両方があります。
きつい面としては、以下のような点が挙げられます。
- 納期の厳しさ
- 権利関係調査の複雑さ
- 実地調査の負担
- 依頼者からのプレッシャー
不動産鑑定士の仕事は決して楽ではありませんが、専門性を活かして社会に貢献できるやりがいのある職業と言えるでしょう。
自らの働き方や得意分野に合わせて業務内容を調整できる柔軟性もあります。
まとめ
不動産鑑定士は、不動産の経済的価値を判定・評価する専門家として、社会的に重要な役割を担っています。
仕事内容は、不動産の鑑定評価を中心に、コンサルティング、調査・分析、国際評価などです。
平均年収は約750万円と高水準であり、経験を積むことでさらに収入アップが期待できます。
独立開業の道も開かれており、自らの裁量で仕事を進められる魅力もあります。
一方で、最終合格率が5%と低い難関試験であることや、試験合格後も実務修習が必要なこと、新規参入の障壁が高いことなど、資格取得から実務開始までの道のりは決して平坦ではありません。
不動産鑑定士に向いているのは、論理的思考力があり、責任感が強く、継続的に学ぶ姿勢を持ち、細部に注意を払え、コミュニケーション能力が高い人です。
仕事にはきつい面もありますが、社会貢献度の高さや専門性を活かせる喜びなど、大きなやりがいも感じられます。
不動産鑑定士を目指す際は、自らの適性や目標、ライフプランと照らし合わせて、長期的な視点で検討することが大切です。
難しい道のりですが、その分、取得後の価値は高く、社会に貢献できる専門家として活躍できるでしょう。